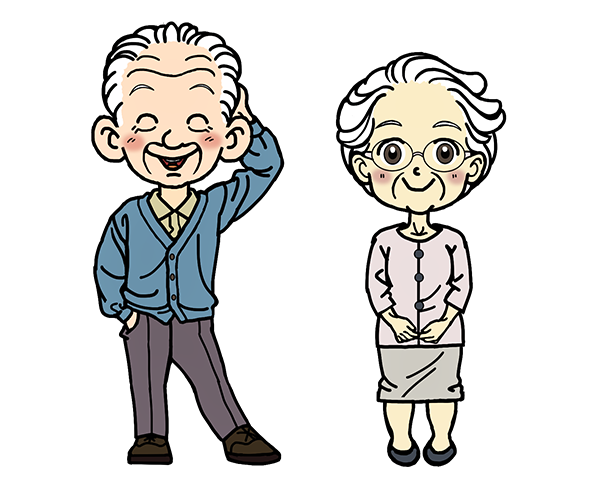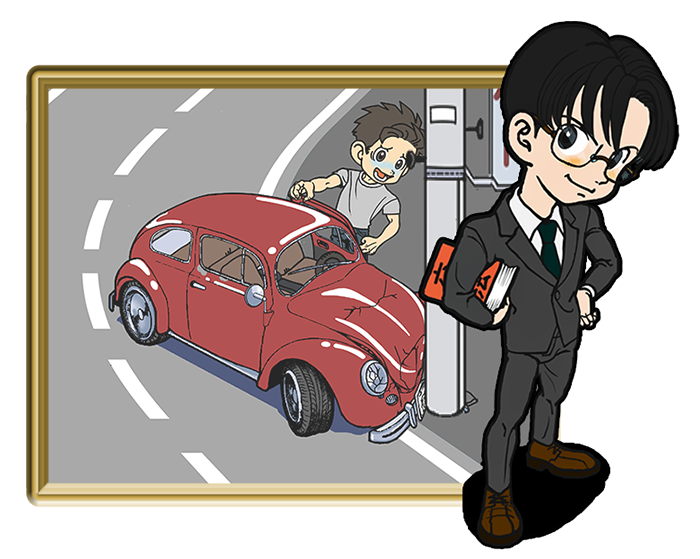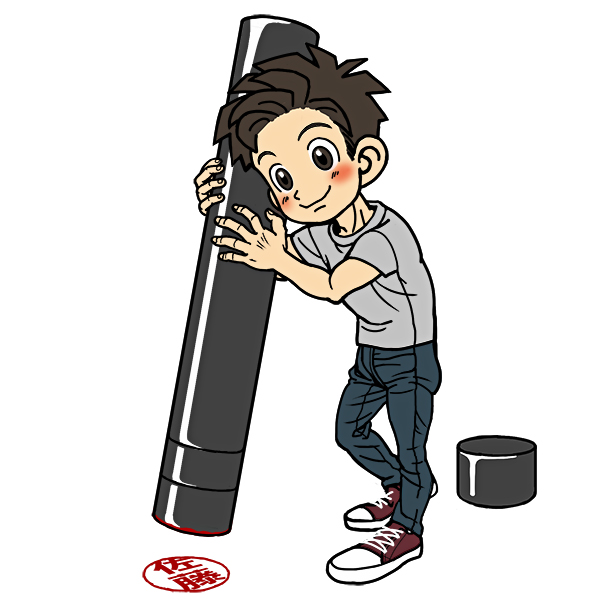個人年金とは保険会社等の民間金融会社が提供する年金保険のことを言います。生命保険の一種だと思っていてOKです。
多くの保険会社の販売員や銀行等金融機関のファイナンシャルプランナー(FP)また金融庁は老後、つまり年金受給時に必要な「貯蓄残高は約3,000万程度」と口を揃えて言います。
老後に2千万円必要とする審議会報告書の議論の過程で、金融庁は「(必要額は)1500万~3千万円」との別試算も示していた。
これは金融広報中央委員会が公表している家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](平成28年)による、老後の一カ月当たり最低予想生活費(27万円)から平均的な年金受給額を引いて、年金受給から平均余命を掛けて算出されています。
例えば女性の場合平均寿命は約87歳ですから退職後(65歳以後)の平均余命は22年間となり以下のような計算になります。
- 予想生活費:月27万円
- 年金受給額:月14万円(厚生年金の平均)
- 平均余命を月加算:264カ月(22年間)
(27万円-14万円)×264=3,432万円
おおざっぱな計算ですが、年金以外にもおおよそこれくらいの貯蓄が必要なのです。
そこで気になるのは老後の貯蓄の選択肢。
老後資金を確保する方法は貯金を除くと主に、以下のものがあります。
- 株式や投資信託等への投資
- 不動産への投資
- 個人年金等の保険商品
中でも個人年金は投資と比べてリスクがなく、投資の知識も不要なので資産運用の初心者の方が検討することが多いと思います。
本ページでは、以下の方向けに、分かりやすく解説します。
「個人年金ってそもそも何?」
「どんなメリットとデメリットがあるの?」
「対面で説明してほしい」
と思う方は無料で相談出来る保険相談サービスを利用してみることをオススメします。
保険相談サービスは専門家に相談しながら今の自分に適した保険プランを選ぶことが出来ます。
Contents
個人年金とはどんな保険?
端的に言えば個人で行う貯蓄型の保険です。
年金という名称がついている通り、所定の年齢(主に60歳~65歳くらい)から年金を受け取ることができます。
公的年金で足りない分を賄う補助的な役割とも言えます。
主に「年金だけでは不安」という方が老後の収入を増やす目的で加入します。
また、詳しくは後述しますが保険商品の一つということもあり、単なる貯蓄、投資目的だけでなく万が一に備える保障も付いてます。
<個人年金>
- 個人年金とは:貯蓄型の保険
- 受け取り:所定の年齢で受け取ることが可能
- 目的:老後の収入の増やし方(貯蓄、投資、万が一に備える保障)
保険会社にお金を預けて増やす
個人年金は保険会社が取り扱いをする保険商品ですが、主の目的はお金を増やすための投資、資産運用です。
多くの個人年金は払込をしたお金(保険会社に預けたお金)の合計よりも受給額(保険業界では返戻金と言われます)が大きくなっています。
払ったお金に対して戻ってくるお金の割合(返戻率と言われる)は商品によって様々ですが、一般的に105%~120%くらいが多いです。
返戻率について
返戻率とは払込をした保険料に対して契約満了時や解約時に返ってくるお金の割合のことです。
例えば毎月1万円、30歳から60歳までの30年間で合計360万円の払込をしたとしましょう。
その場合、返戻率が105%の保険であれば満了時に378万円返戻金としてお金が戻ってきます。払込した分の5%、18万円が儲けとなります。
同条件で返戻率120%なら432万円の返戻金となりリターンは72万円です。
これにプラスして万が一の保障もあるので金利がほぼゼロに近い銀行に預金をするよりメリットは大きいです。
個人年金を含め生命保険は賛否両論ありますが、返戻率が100%を超えるものであれば単に銀行に定期預金するよりもずっとリターンは大きいのです。
保険会社はどうやってお金を増やしている?
投資や資産運用にあまり詳しくない方は、
「保険会社に預けるだけで掛け金以上の年金が受給出来て、さらに万が一の保障もあるなんてどうなってるの?」
「保険会社は儲かっているの?」
と思うかもしれません。
が、保険会社は顧客から集めたお金で債券や株式等を購入して資産運用をしているのでそこから利益が出ています。
「投資なんてリスクが高いんじゃないか?」
2016年の夏頃に5兆円の年金損失報道があり、その際に国が国民から徴収した国民年金で株や債券の投資をしていることが話題になりましたが、実は国も銀行も郵便局(現ゆうちょ銀行)も保険会社も何十年も前から株や債券へ投資をしています。
金融投資は馴染みのない人にとってはリスクの高いことのように思えますが、資産の大きい機関投資家(銀行や保険会社等の金融機関)はある程度安定的にお金を増やすことが出来るのです。ここでは詳しい解説は省略しますが…
ちなみに5兆円の赤字があった年金の運用も翌年(つまり2016年度)には黒字に転換し、運用資産額も最高値となっています。
実は金融機関にお金を預けてリターンがないのは超低金利の今の銀行くらいで、バブル期だと郵便局に預けるだけで年利8%くらいのリターンがあったんですよね…
つまり保険会社は顧客から預かったお金で資産運用をして、一部顧客に保障や返戻金として返還してその差額分で利益を得ています。
個人年金の種類と違いについて
個人年金は大きく分けて、以下の4種類があり、それぞれ組み合わさってできています。
- 円建てで積立する円建て保険
- 外貨建てで積立する外貨建て保険
- 金利が確定している(変動しない)確定保険
- 金利が変動する変額保険
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 円建て確定型 | 円で積立をして金利が確定している。 |
| 外貨建て確定型 | 外貨で積立をして金利が確定している。 |
| 円建て変額型 | 円建てで積立をして金利が変動する。 |
| 外貨建て変額型 | 外貨建てで積立をして金利が変動する。 |
円建て個人年金
日本円で保険料を積み立てる個人年金です。
個人年金は貯蓄性のある保険ですから、単純に日本円で保険会社にお金を預けるというイメージでOKです。
ただし、現在は日本国内の予定利率が低い(利回りが少ない)ため、あまり大きな運用をすることは難しくなりました。
そのため最近は後述する外貨建ての商品が注目されています。
外貨建て個人年金
保険料の積み立てと年金の受け取りを外貨(主に米ドルやオーストラリアドル等)で行う個人年金です。
上記の通り円の金利が低い為、外貨建ての方が利回りが大きい場合が多いです。
ただし、以下の2つのデメリットがあります。
- 受け取った年金を外貨から日本円に換算する際に手数料がかかること
- 年金を受け取る時の為替レートによって日本円で受け取る金額が変動してしまうので、元本割れの可能性があること
1つ目を為替コスト、2つ目を為替リスクと呼びます。
1つ目の為替コストに関しては一般的に公開されていないので(※2017年7月現在)、あまり意識する必要はないと思います。円建てに比べて余計な手数料が掛かっているということだけ知っておくと良いかも。
2つ目の為替リスクに関しては保険に限らず外貨の商品には必ず付きまとってくるリスクです。
例えばアメリカドル建てで払込をしていて、日本円での受け取り時に円高(円の価値が上がってドルの価値が下がる)になると予定していたよりも受取額が少なくなってしまいます。
確定個人年金
金利があらかじめ確定されていて、受給できる年金額が決まっている種類の個人年金です。
返戻率がはじめから決まっている為、払い込んだ保険料に対する返戻率が110%の確定個人年金であれば、確実に保険料の110%の年金が受け取れるということです。
損することはありませんが、金利が低いので運用によって年金額を増やすことは難しいのが特徴です。
変額個人年金
確定年金に対して金利が変動し、受給額も変わってくるのが変額個人年金です。
運用実績(主にその時の経済状況で決まる)に基づいて保険金や年金、解約返戻金などが変動するのが特徴です。
金融市場の影響を受けて金利が変動するため、運用状況が良くないと将来受給する年金額が減る可能性があります。
ただ、多くの変額年金は金利の最低ラインが設定されているため赤字になることはありません。
また、リスクがある一方でインフレに対応でき、運用次第では年金額を大幅に増やすことが出来るというメリットもあります。
個人年金のメリット
個人年金に加入すると主に以下の4つのメリットがあります。
- 確実に貯蓄ができる
- 所得控除によって節税ができる
- 持病があっても加入できる商品がある
- 万が一の保障もある
確実に貯蓄ができる
自分で貯蓄するより、保険料を支払うという形で強制的に積み立てができるので、確実に貯蓄ができます。
また、(詳しくは後述しますが)途中で解約すると受け取れる返戻金がそれまでに支払った保険料より少なく損することが多いので、それを防ぐためにかえって継続できるという見方もできます。
自身で銀行などで貯蓄した場合、お金をすぐ引き出してしまいそうな人におすすめです。
所得控除によって節税が出来る
個人年金保険料控除という、所得税法により認められた制度を受けることができます。
1年間に支払った個人年金保険料のうち、所定の額を所得から控除することができ、それによって所得税と住民税を軽減することができるのです。
例えば個人年金保険料を年間8万円以上払った場合、所得税で4万円、住民税で2万8千円の控除を受けることができます。
所得控除について
上記の所得税4万円、住民税2.8万円の控除はこの金額がそのまま税金免除されるわけではありません。
実はこれはあくまで所得控除額の話で、実際安くなる税金はもう少し安いのです。
まず所得税から解説すると、所得税は所得に応じて計算されます。
下の表が所得税の計算方法です。
| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 千円~194.9万円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329.9万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~649.9万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~899.9万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1,799.9万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円~3,999.9万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
この課税所得額というのを求めるのにもまたやや複雑な解説が必要になるので本ページでは省略しますが、一般的に会社員で年収500万円の人は課税所得額が195万円~329.9万円に該当し、税率10%が適用されます。
生命保険控除はこの課税所得額が控除されるというものです。
なので、年収500万円の人が生命保険控除によって4万円の控除を受けると、課税所得額が4万円引かれ、結果そのうちの10%分税金が安くなるというわけです。
一例を挙げると、年収500万で課税所得額が300万円だったとした場合、所得税は202,500円となります。
【300万×10%-9万7500円=20万2500円】
ここで生命保険控除が4万円あると、課税所得額が296万円となり、所得税は19万8500円となります。
【296万円×10%-9万7500円=19万8500円】
つまり4,000円の節税効果となるわけです。
ここまでが所得税の節税です。
ここからさらに住民税が引かれるわけですが、住民税の場合一律10%の税率となるので、2.8万円の控除があった場合、2,800円の節税となります。
合計で6,800円の節税となるわけです。
1年間だけ見ると少ない金額に見えるかもしれませんが、保険払込期間が30年だとすると6,800円×30年=204,000円もの節税効果があるわけです。
持病があっても加入できる商品もある
一般的に生命保険などは持病がある人と健康な人とでは入院する確率や死亡する確率が違うため、加入の際に健康状態の告知が必須となります。
しかし個人年金は貯蓄の意味合いが強い保険であるため、基本的には加入の際に健康告知の必要はありません。
ただし医療特約などの特約をつけたい場合など、場合によっては健康告知が必須であり、内容によって加入できないこともあります。
万が一の保障もある
個人年金は保険商品ということもあり、預金だけでなく万が一の保障もあるものがほとんどです。
保障内容は各生保会社が提供する保険商品によって変わってきますが一般的に、以下の2つは付帯していることがほとんどです。
- 死亡保障(払込時に万が一被保険者が死亡した場合一定の保障が受けられる)
- 高度障害保障(払込時に万が一被保険者が高度障害となった場合保障が受けられる)
また、年金の受け取り方法にも種類があり、確定年金型の個人年金は受け取り途中で本人が死亡しても、受給が決まっている範囲まで遺族は年金を受け取ることが出来ます。
個人年金のデメリット
主に以下のような4つのデメリットもあり、中でも注意したいのが銀行預金と違って元本割れする可能性があることです。
- 中途解約すると元が取れない
- 元本割れのリスクがある
- 個人年金を扱う会社が倒産するリスクがある
- インフレの影響を受ける
中途解約すると元が取れない
個人年金は保険料を払込期間内に支払うことを条件に、積み立てた金額を将来年金として受け取れる保険です。
ただし、途中で解約するとそれまで支払った保険料より受け取る解約返戻金の方が少ない可能性があります。どのくらいの期間支払えば返戻率が100%を超えるのか、は商品によって変わってきます。
逆にそのことが拘束力となって確実に積み立てができる商品とも言えます。
元本割れのリスクがある
外貨建てや変額年金などの中には、元本割れするリスクがあります。
そもそも個人年金保険の中には万が一の保障が手厚くてリターンがほとんどないものもあったりします。
加入する前にどのようなリスクがあるのか、しっかり確認しましょう。
個人年金を扱う会社が倒産するリスクも
個人年金は民間の保険会社が扱っている保険商品です。
安易に保険料が安いからと言って契約して、保険会社が倒産するリスクもゼロではありません。
保険会社が倒産した際には、生命保険契約者保護機構が契約を保護してくれる制度になっていますが、保障額が下げられたり積立金が一部減額される可能性が高いので注意が必要です。
インフレの影響を受ける
円建ての個人年金などは、インフレに対するリスクがあることも注意しておく必要があります。
インフレとは物価上昇のことで、貨幣価値が下がることを意味します。
保険料を払っている期間内にインフレによって円の価値が下がった場合、将来受け取る年金額は変わらないため加入時と比べて実質的に受け取る金額が減ってしまう可能性があります。
ただし、変額個人年金であれば払い込んだ保険料の積み立て部分が投資信託として運用される為、インフレの影響を受けにくいと言えます。
まとめ
個人年金は大きく4つの種類があります。
- 円建て個人年金
- 外貨建て個人年金
- 確定個人年金
- 変額個人年金
個人年金のメリットは主に以下の3つです。
- 確実に貯蓄ができる
- 所得控除によって節税が出来る
- 持病があっても加入できる商品もある
個人年金のデメリットは主に以下の4つです。
- 中途解約すると元が取れない
- 元本割れのリスクがある
- 個人年金を扱う会社が倒産するリスクも
- インフレの影響を受ける
以上の個人年金のメリット・デメリットを踏まえて、自身のライフプランに合った個人年金を検討してみましょう。
無料保険相談サービスを活用しよう
「保険とか難しくてよくわからない」
という人は無料保険相談サービスを利用してみましょう。
10年くらい前は、保険は生保会社の販売員を通じて加入するのが当たり前でしたが、最近は保険の窓口を始めとする保険相談サービスを利用する人が増えてきました。
無料保険相談サービスとは生命保険会社の販売員が自社の保険を勧めるのではなく、保険の専門家(ファイナンシャルプランナー)が複数の保険商品から利用者に最も適した保険を選定して提供するサービスです。
保険相談サービスは複数社(十数社)の保険会社が提供する保険商品を取り扱っているため選択肢が多く、自分の生活環境に合わせた保険が見つかりやすいです(FPが提案してくれます)。
無料保険相談には保険の窓口やイオン保険のようなこちらから店舗の窓口に出向いて相談するものと、FP(ファイナンシャルプランナー)とあらかじめ打ち合わせして近くのファミレスやカフェで相談するものがあります。
保険相談サービスを検索出来る保険ニアエルは、全国にあるおすすめの相談窓口を検索することができます。
以前私自身、ニアエルを利用して相談を受けたことがありますが、無理に加入を勧められることもないので安心して利用できました。
こういった無料の保険相談のサービスはその場ですぐに加入しなくても問題ありませんので試しにお話だけでも聞いてみると良いですよ。
執筆者:鄭 恵美
「生命保険に加入したいけどどれがお得なのかわからない」
「保険料の負担がきついから解約しようか迷っている」
「自分にとって一番最適な保険に入りたい」
現在日本で加入できる生命保険会社は数十社にのぼり、各社それぞれたくさんのプランを提供しているため、一人で保険選びをするのは非常に難しいです。
保険のビュッフェが提供する無料保険相談サービスでは、保険の専門家(ファイナンシャルプランナー)があなたに最適な保険を紹介してくれます。
保険相談は無料で出来ますし、もちろん「お話だけ聞いて加入しない」でもOK!
ご検討ください。
※保険の見直し一つで年間数万円以上の保険料が変わってくることもあります