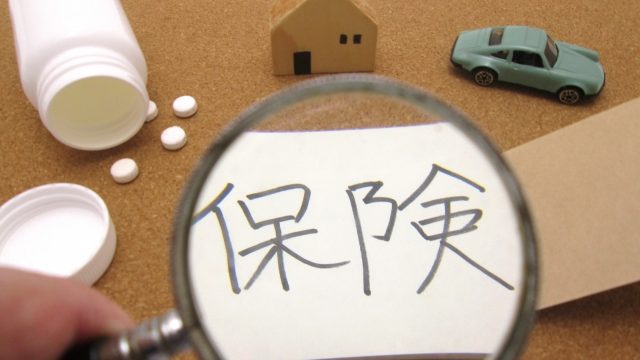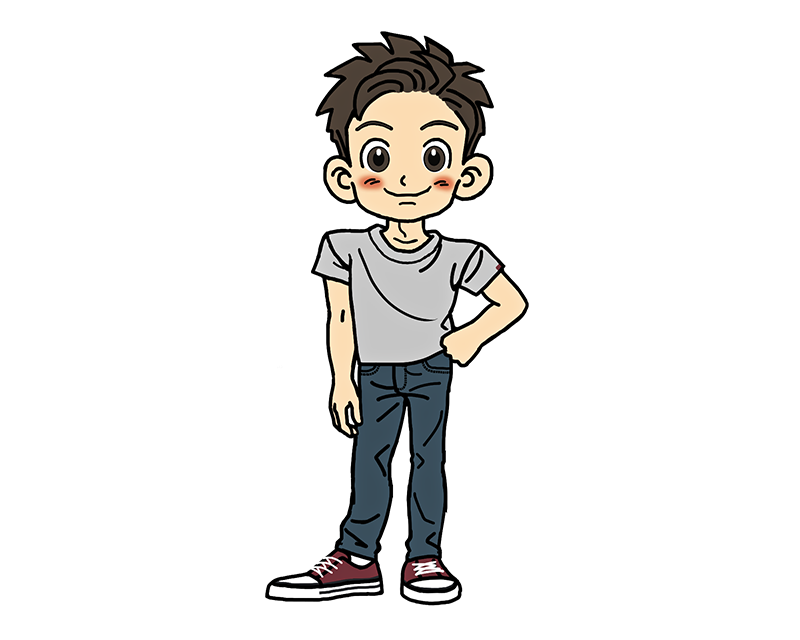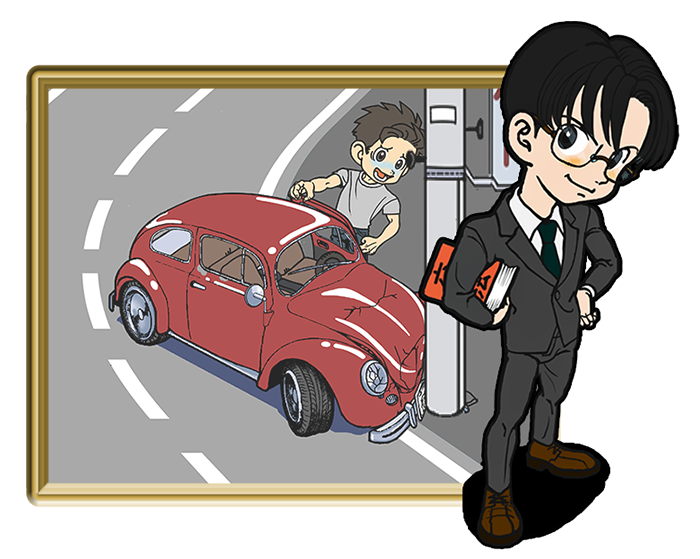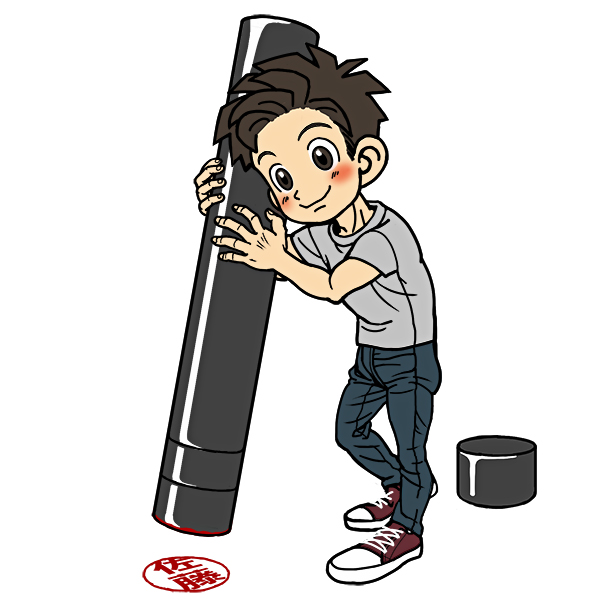学資保険に限ったことではありませんが、保険は契約者(契約をする人)と被保険者(保険の対象となる人)、保険金受取人をそれぞれ別の人にすることが可能で、契約時に分かりにくいと感じる人も多いと思います。
「保険金の受取人を誰にするか」なんてあまり深く考える人は少ないと思いますが、学資保険は保険金の受取人を誰にするかで掛かってくる税金が変わってきます。
本ページでは「学資保険の契約の仕方、特に受取人が違うとどのような影響があるかについて」解説します。
Contents
保険契約の基本
保険契約では、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者が必要です。
- 保険契約者:契約者であり、普通は保険料負担者となります。
- 被保険者:保険の対象者です。被保険者が所定の状態になったときに、要件を満たしたときに保険金や給付金が支払われます。
- 保険金受取人:保険の支払事由に該当した場合の保険金を受け取る人です。
上記3者はそれぞれ違う人にすることも可能で、学資保険の場合は一般的に保険契約者及び保険受取人が両親のどちらかや祖父母等、被保険者が子どもになります。
ちなみに詳しくは後述しますが保険契約者と保険金受取人は同じ人にした方がお得です。
学資保険と他の保険との違い
学資保険と他の生命保険には決定的な違いがあります。それは、「保険料免除特約をつけることで保険料が免除にされること」と「満期保険金を受け取ることができる」です。
例えば医療保険の場合被保険者が所定の病気のときに給付金が支払われます。そのため告知書や健康診断書に記入するのは被保険者となります。がん保険や死亡保険も同様です。
しかし学資保険の場合、被保険者は子どもです。
保険契約者が万一のとき保険料免除特約を付けておけば保険料が免除される上に、満期保険金も受け取れます。
そのため学資保険に限っては、健康状態の審査対象は保険契約者となります。
残念ながら被保険者が亡くなった場合は既払保険料相当額が戻ってきます。
学資保険契約パターンと税金
契約には保険契約者・被保険者・満期保険金受取人が必要ですが、誰にするかによって契約内容が変わってきます。
保険契約者は原則、被保険者の父母であり扶養している親族です。学資保険は保険契約者に年齢制限をかけており、祖父母が保険契約者になれるかどうかは確認が必要です。
また学資保険の場合、保険契約者の健康状態をみるのでその点も注意が必要です。
被保険者は子どもですが、受取人は普通保険契約者になります。受取人を配偶者や子にした場合は課税方式が変わります。また第三者は余程特殊なケースでない限り認められないでしょう。
ですので保険契約者や満期保険金受取人は親族(父母、子、場合によっては祖父母や孫)がなるのが一般的です。
では契約パターンについて見ていきたいと思います。
満期保険金受取人が夫(保険契約者)
| 保険契約者 | 被保険者 | 満期保険金受取人 |
| 夫 | 子 | 夫 |
この場合、受取時に一括受け取りなら所得税(一時所得)の対象となります。一時所得は以下の計算式で求めます。
(受取額-保険料)-最高50万円
つまり利益が50万円以下であれば課税されないことになります。あくまで利益です。
利益とは得た保険金から払込保険料の総額を引いた金額のことです。
仮に50万円を超えてしまった場合を見てみましょう。
例えば、返戻率130%の商品ですと、支払保険料累計額300万円に対して、受取額は390万円となります。上の式にあてはめますと、
(390万円-300万円)-50万円=40万円
40万円が一時所得の金額となります。次にこの金額を給与所得者なら給与所得と合算しますが、合算するときに2分の1することができるので、20万円を合算します。
給与所得が330万円超695万円以下なら税率は20%なので、20万円×20%=4万円の税額負担増となります。また住民税は10%なので、20万円×10%=2万円で、所得税・住民税合わせて6万円の負担増となります。
なお、税を加味した返戻率を求めると、
390万円-6万円=384万円
384万円÷300万円×100=128%
となり、2%返戻率が下がります。
税負担が気になる場合、受取金額を必要な大学費用の半分150万円ぐらいにおさえると、返戻率が130%だとしても、
(195万円-150万円)-45万円(※)=0
※(受取額-保険料)が50万円以下の場合はその金額を差し引きます。
※ほかに一時所得がある場合は、最高50万円引くことができます。
上記のとおり50万円以下におさまります。全額を学資保険に頼ると保険料の負担や保険会社の破たんの際に困ってしまいますので、半額は貯蓄で準備するのも一つです。
満期保険金受取人が妻(保険契約者の配偶者)
| 保険契約者 | 被保険者 | 満期保険金受取人 |
| 夫 | 子 | 妻 |
この場合、受取時に贈与税の対象となります。贈与税には基礎控除があり、年間110万円なら非課税となります。
贈与税は所得税と違い利益ではなく、受け取った保険金に対して課税されます。
贈与税は基礎控除後の金額が200万円以下で10%の税率がかかります。受取額が310万円なら、
310万円-110万円=200万円
200万円×10%=20万円
となり、贈与税で20万円支払う必要があります。
満期保険金受取人が子(保険契約者の子)
| 保険契約者 | 被保険者 | 満期保険金受取人 |
| 夫 | 子 | 子 |
この場合も、受取人が配偶者と同じく受取時に贈与税の対象となります。子が贈与税を支払うことになります。
つまり満期保険金受取人が妻や子の場合、受取額310万円のうち20万円は納税のため使用できないことになります。学資保険は死亡保険のように金額が大きくないため、20万円の課税は負担が重くなります。
まとめ
学資保険に限りませんが、贈与税は税率が高いのでほかの課税を選択した方がいいです。
学資保険の場合も一時所得として所得税を課税された方が税負担はゼロか少なくて済みます。一時所得は所得税の中でも課税負担が軽い部類ですのでお勧めです。
結論としましては保険契約者と満期保険金受取人を同じにすべきです。
「生命保険に加入したいけどどれがお得なのかわからない」
「保険料の負担がきついから解約しようか迷っている」
「自分にとって一番最適な保険に入りたい」
現在日本で加入できる生命保険会社は数十社にのぼり、各社それぞれたくさんのプランを提供しているため、一人で保険選びをするのは非常に難しいです。
保険のビュッフェが提供する無料保険相談サービスでは、保険の専門家(ファイナンシャルプランナー)があなたに最適な保険を紹介してくれます。
保険相談は無料で出来ますし、もちろん「お話だけ聞いて加入しない」でもOK!
ご検討ください。
※保険の見直し一つで年間数万円以上の保険料が変わってくることもあります